投資をやめたくなる人の共通点
「NISAを始めたけど思ったほど資産が増えない」
「株価が下がると怖くなって売ってしまった」
「一時的な損で気持ちが折れた」
こういった理由で投資をやめてしまう人は少なくありません。事実、野村アセットマネジメントの2024年調査によれば、投資を辞めた理由のトップ3は以下の通りです:
- 思ったより儲からない(期待とのギャップ)
- 損失が怖い(リスク許容度の不足)
- 資金が続かない(計画性の不足)
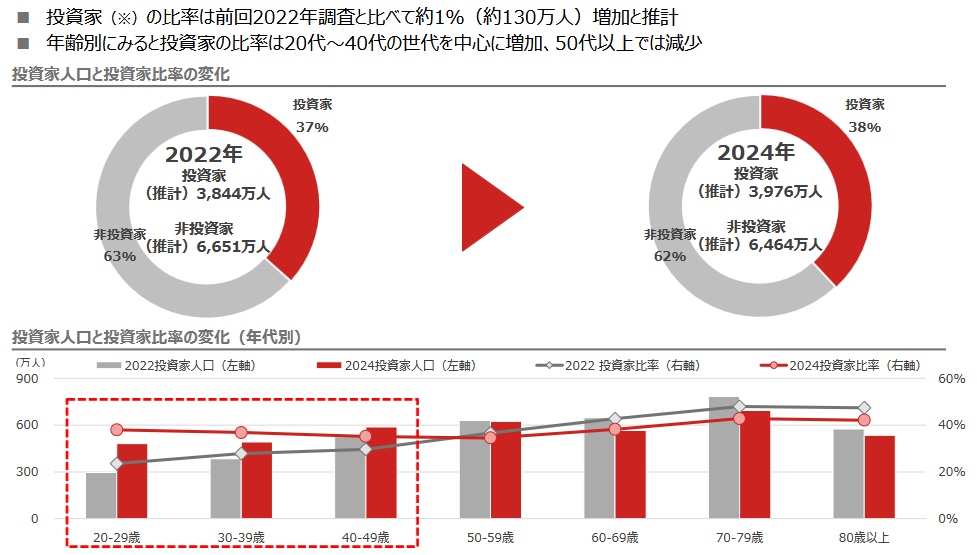
出典:野村アセットマネジメント https://www.nomura-am.co.jp/corporate/surveys/pdf/20240418_52B4DE55.pdf
さらに、世代別で見ると20〜40代の投資家は増加傾向にある一方、50代以上では減少している傾向が見られます。つまり、若い世代は感情に左右されず、継続しやすい構造を持っている可能性が高いということです。
投資を続ける人だけが資産を築ける理由
筆者もかつては投資初心者でした。最初はFXに手を出して失敗。しかしそこから米国株インデックス投資にシフトし、毎月自動で積立するスタイルに変更しました。
その結果、5年以上にわたり資産は右肩上がりに増えています。とくに、S&P500やNASDAQにコツコツ積立をする「ドルコスト平均法」が効果的でした。
ここで注目したいのは「複利の力」。たとえば:
- 月3万円を年利6%で20年間積み立てると…
- 約1,400万円(元本720万円の約2倍)
このように、短期で儲けるのではなく、時間を味方につけて淡々と積み上げることが、資産形成の近道なのです。
プロスペクト理論とは?“損”の痛みが行動を狂わせる
人は「得」よりも「損」のほうが強く記憶に残る。
これを説明するのが、ノーベル経済学賞を受賞したプロスペクト理論です。
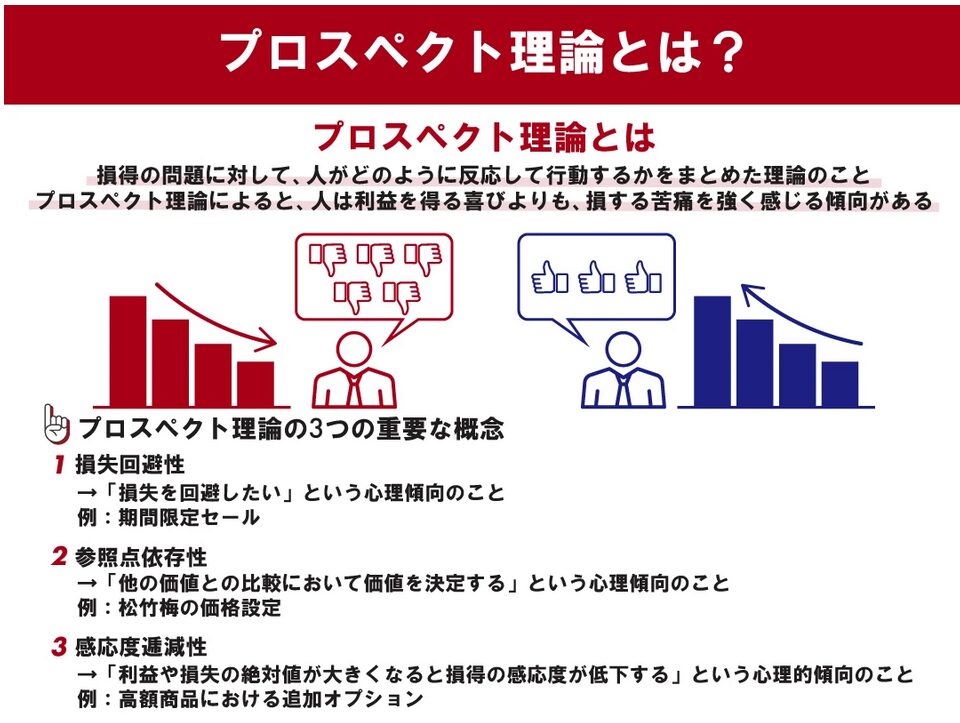
出典:ツギノジダイ https://smbiz.asahi.com/article/14834884
| 心理効果 | 内容 | 影響例 |
|---|---|---|
| 損失回避バイアス | 同じ金額でも損の方が痛く感じる | 少しの下落でもすぐ売ってしまう |
| 参照点依存性 | 他人と比べて判断する | SNSで儲かってる人を見て焦る |
| 感応度逓減性 | 得れば得るほど感動が薄れる | 投資に満足できず次に手を出す |
これらは全て人間の本能的な反応です。だからこそ、「意志が弱い」わけではなく、仕組みで防ぐしかないのです。
投資を辞めたくなる瞬間とその対処法
- 暴落相場(例:コロナショック・米金利上昇局面)
- 友人が儲かっているのをSNSで見たとき
- 利益確定した直後にさらに値上がりしたとき
こうした時に「判断しない・感情に従わない」ために、以下を徹底しましょう:
- 自動積立設定を活用する
- 購入後は株価を見ない
- 毎月の積立額だけを見て“習慣化”する
投資を続ける人が実践する「3つの黄金ルール」
① リスク許容度の範囲で投資する
- 生活費の3〜6ヶ月分は現金で確保
- 「最悪ゼロでも生活に影響なし」の金額で運用
② 短期で一喜一憂せず、10年スパンで見る
市場は常に上下するが、長期では右肩上がりが基本。
「今」は買い場になることも多い。
③ 淡々と積み上げる投資を仕組み化する
- 毎月定額でインデックス投信を自動購入
- 配当や評価損益は気にしない
- 再投資で口数を積み上げる戦略がベスト
投資をやめた人が“再挑戦”するための3ステップ
ステップ①|「やめた理由」を客観視する
- 感情に振り回された?
- 資金が足りなかった?
- 情報収集が不十分だった?
ステップ②|少額・自動・長期を前提に再開
- 月1万円など、少額から再開
- 積立NISAやiDeCoの制度を活用
- 自動積立で“ほったらかし”にする
ステップ③|情報とメンタルを定期チェック
- 3ヶ月に1回程度、運用状況を見直す
- SNSで他人と比べない
- 自分の「目的軸」で継続判断する
投資で成功する人と失敗する人の決定的な違い
| 続ける人 | やめる人 |
|---|---|
| 感情より仕組みを信じる | 不安で売買を繰り返す |
| 少額でも継続重視 | 初期の損失で脱落 |
| 自分軸で判断 | 他人の影響で右往左往 |
最後に|「続ける力」はお金よりも強い武器になる
投資は、お金を増やすための手段です。
でもそれ以上に、「感情をコントロールし続ける力」を養うツールでもあります。
- 未来に希望を持つ
- 家族の生活を守る
- 自分の働き方や人生の選択肢を広げる
これらを叶えるには、「続けること」しかありません。
辞めるのはいつでもできる。でも、続ける人だけが未来を変えられる。










